他の楽器ではこういう名前は使いませんが、音型は分散和音なので木管も一緒に練習するといいでしょう。
木管も含めたリップスラー音型の楽譜 (PDFファイル)
唇とその周りの筋肉の柔軟性を付けるためや音域による舌の位置を覚えるためにも、リップスラーは金管楽器の基本練習の中で大変重要なものです。
金管楽器は、ごく一部に例外もありますが、ピストン(ロータリー)を押さえていない時、それを”0”と表記します、管が一番短くて音は一番高く、以下「2」→「1」→「1+2または3」→「2+3」→「1+3」→「1+2+3」の順にピストンを押さえるとだんだん息の通る管が長くなって、出る音は半音ずつ低くなっていきます。
吹く人に近いピストンから1、2、3と番号を付けています。それぞれ人さし指、中指、薬指で押さえます。
これはどの金管楽器も共通です。
トロンボーンは1ポジションから7ポジションがそれぞれの指使いに当たりますが、小学生の場合7ポジションまで使える(手が届く)生徒は少ないので、まず6(または5)ポジションまでを正確にとる練習をしましょう。
例えばトランペットやアルトホルン(in Bb のトロンボーン、ユーフォニアムやチューバ)でド-ソ-ドというパターン
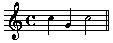 をスラーで練習してから指使いを上記の順に変えていくと、同じパターンを半音ずつ六段階下げていくことができます。
をスラーで練習してから指使いを上記の順に変えていくと、同じパターンを半音ずつ六段階下げていくことができます。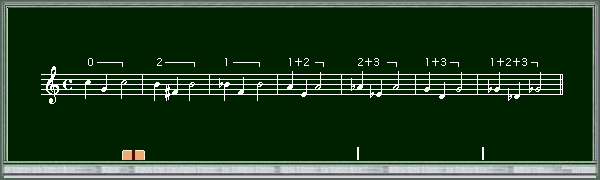
同じパターンをユーフォニアムのために実音で書くとこうなります。トランペットの1オクターブ下の音です。
トロンボーンの1から7ポジションでも同じパターンが吹けます。
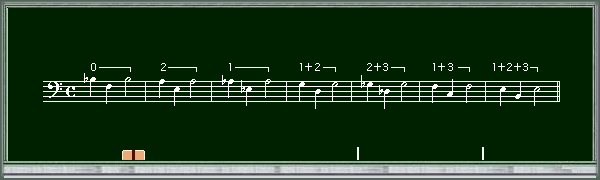
Bbチューバは同じ指でこのオクターブ下の音が出ます。
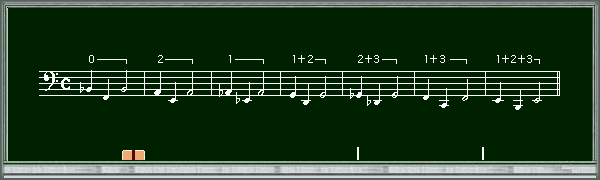
生徒にとってはある音程のパターンを覚えると指を変えるだけでそのまま7通りの移調ができ、楽譜を考えなくても案外簡単に音域を広げることができます。
初めは上の楽譜のように、ある音からすぐ上か下の倍音に移って元の音に戻る練習から始めてください。次に同方向に二つの音を吹いて元の音に戻ってくるようなパターンや上下に一つずつ動くパターンで少しずつ音域を広げ、それを繰り返したり組み合わせたりして長いフレーズにしていきます(リップスラーの例)。
一つのパターンを吹いている間はスラーで息を止めませんから、ロングトーンと同じように息やアンブシュアをコントロールする練習にもなります。ロングトーンで8拍、16拍と音を延ばせる生徒はそれと同じくらいの長さのパターンを吹けるはずです。
リップスラーのパターンは各金管楽器の教則本にいろいろ紹介されていますが、倍音表の音から選んで思いつくままに並べれば誰でも作ることができます。
「楽譜置き場」の「合奏前の基本練習のために」に木管楽器も一緒に吹けるリップスラーの楽譜を出しています。木管楽器にとっては簡単なアルペジオ(分散和音)の練習になります。
同じ音型で全部の音をタンギングして吹くと、アンブシュアを強くするためのいい練習になりますから、一つのパターンを1度目はスラーで、2度目はタンギングして吹くのもいいでしょう。