まず合奏の前に一人一人が口慣らしを(ウオーミングアップ)するように習慣付けましょう。合奏が始まるまで静かに音を出して楽器を暖めておきます。
合奏での基本練習も楽譜に従って進めていきます。楽譜を読むことも基本練習の一つです。この部分は各バンドである程度内容を決めて生徒だけでも出来るようにしましょう。
先生が聞ける時には間違いを見つけてやり直したり必要なものを追加したりして、お互いの音も聴かずに毎回通過するだけの基本練習にならないように気を付けましょう。
ブラスバンド(金管バンド)の音作りには「金管バンドのためのデイリー・トレーニング」がいいと思います。すでに多くの学校で使われていますが、一部しか音を出していないバンドが多いようです。時間がない時は繰り返しを省略しても最後のコラールまで練習してください。音階もここにある三つの調は最低限練習しましょう。
吹奏楽のためにはいくつかのバンドメソードが出版されています。それぞれのバンドに合ったものを選んでその通りに練習してください。
書いてあることをきちんと守って使えばどれも価値あるものだと思います。
あまりどのメソードにも書いてないのですが、短い音符をみんなで合わせる(縦の線を揃える)練習も大切です。例えば四分音符一つをテンポに合わせて吹きます。
楽譜にするとこうなります。
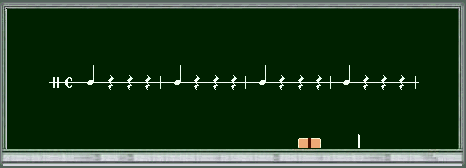
この形でメトロノーム
 に合わせて、同じ音を繰り返したり、音階を吹いたりします。余韻の形まで合うように注意します。
に合わせて、同じ音を繰り返したり、音階を吹いたりします。余韻の形まで合うように注意します。一つ一つの音をもっと短く、例えば十六分音符のように、しかも大きな音で吹くと音の立ち上がりを鋭くはっきりさせる練習にもなり、息の力も強くなります。
楽譜にするとこうなります。
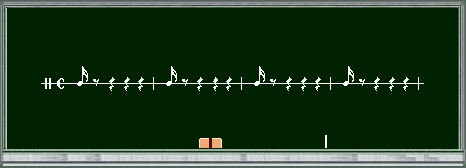
打楽器はスネアドラム、シロフォン、ウッドブロックのような余韻の短いもので合わせます。
テンポは四分音符120くらいから始めて、ドンドン速くしていくと集中して練習できます。三拍子でも練習してください。
パートごとや音域でバンド全体を二つに分けて一方を四拍子、一方を三拍子で同時にスタートすると楽しく練習が出来ます。
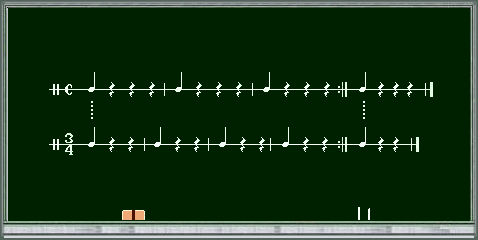
ただ、「6. 合奏の場所と必要なもの」でも書きましたが「電気のメトロノームにスピーカーをつないで大音量で鳴らしながら練習」するのはやめてください。
バンドの演奏のテンポが遅れ始めるとほとんどの場合、先生の指揮もバンドに合わせて遅くなっています。バンドに負けずに正確なテンポで指揮を続けるのはなかなか大変です。
例えば、先生がメトロノームが左右に振れるのを見ながら、あるいは電子メトロノームの音をイヤホーン等で聞きながら正確なテンポで指揮を続ければ、バンドもだんだんと正確なテンポで演奏できるようになってきます。
多くの場合、問題は指揮者だけで解決できます。
音階も全音符ばかりではなくマーチ・テンポの八分音符くらいまではみんなで練習してください。
基本練習というと機械的に音を出す練習だけを考えがちですが、ユニゾンでメロディを吹いたり周りの音程を聴きながらコラール等を吹くことも大切な基本練習です。何曲かのコラールを用意し、コラールのスタイルにも慣れるように練習しましょう。
また、<金管バンドのための編曲集>にあるような簡単な曲を、毎回の練習で何曲か通すことも有意義な基本練習になると思います。
吹奏楽ならマーチ集の楽譜を持っていると楽しく練習しながら基本的な技術を身に付けることが出来ます。