楽譜に書いてある音と実際に出る音が違う楽器のことを移調楽器と言います。
これは楽器の構造上の分類ではなく演奏上の都合で考えられたもので、金管楽器(トランペットやホルン)ではピストンがなく自然倍音(その調のド、ソ、ド、ミ、ソ・・・)
 しか出なかった頃からの伝統、また木管楽器では同じ運指で同族のいくつかの調の楽器(例えば変ホ、変ロ、アルト、バスのクラリネットやソプラノ、アルト、テナー、バリトンのサックス等)が吹けるという融通性のために楽譜を移調して書いています。
しか出なかった頃からの伝統、また木管楽器では同じ運指で同族のいくつかの調の楽器(例えば変ホ、変ロ、アルト、バスのクラリネットやソプラノ、アルト、テナー、バリトンのサックス等)が吹けるという融通性のために楽譜を移調して書いています。トロンボーンはその前身のサックバットの頃から、スライドを使って半音階のすべての音を出すことができましたから、昔から実音楽器として扱われてきました(イギリスのブラスバンドでの扱いは例外です)。
例えば、ソプラノリコーダーの最低音のド
 と同じ(全部の指を押さえる)運指を、アルトリコーダーではファ
と同じ(全部の指を押さえる)運指を、アルトリコーダーではファ と覚えます。これは実音楽器の考え方で、これをソプラノもアルトも同じ運指を覚えてアルト用の楽譜は実音よりも5度上げて(ファをドに)書くというのが移調楽器の考え方です。
と覚えます。これは実音楽器の考え方で、これをソプラノもアルトも同じ運指を覚えてアルト用の楽譜は実音よりも5度上げて(ファをドに)書くというのが移調楽器の考え方です。このように移調楽器や実音楽器があることがバンドの指導を難しく(少なくとも難しそうに)していることは間違いありません。初めてバンドのスコアを見ても実際に鳴る音がわかりにくいですし、ピアノ等で音を確かめるにも移調の知識が必要です。
吹奏楽を指導している人の中には自分で実音のスコアを作っているという方もいらっしゃるようですが、時間的にも大変だと思います。
Bbのクラリネットやトランペットは、楽譜よりも一音(長二度)低い音が出ます。
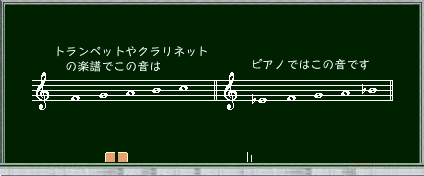
Ebのアルトサックスやアルトホルンは楽譜よりも長六度低い音が出ます。
in Ebのト音記号のパート譜はそのままへ音記号で読んで調号にフラットを三つ増やせば実音(オクターブ上)に読み替えることができます。
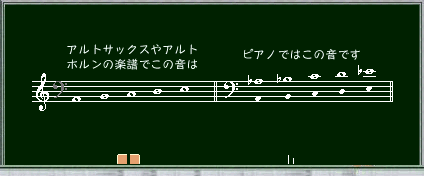
同じin EbでもEbクラリネットやEbコルネットは楽譜よりも短三度高い音が出ます。
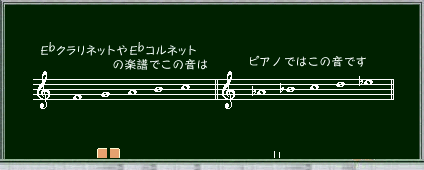
Fのホルンは楽譜よりも五度(完全五度)低い音が出ます。
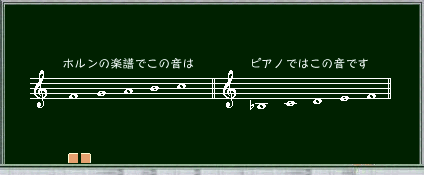
この頃は簡単に移調できるキーボードがありますから、それを使って調を設定すればそれぞれのパート譜をそのまま弾くだけでその楽器の音程が出せます。