もう、自分がどのようにして楽譜を読めるようになったかを思い出せない方も多いのではないかと思います。
楽譜は、音楽用語とか音楽的なニュアンスを別にすると、いつから(何拍目から)、どの高さで、どれだけの長さの音を出すかを表しています。いつからと音の長さを合わせるとリズムになります。ですから楽譜を読む練習は音の高さとリズムとに分けて考えれば分かりやすいと思います。
音の高さはまず楽譜のどの位置がどの音を表しているかを覚えることから始めます。
こういうところからきちんと教えて下さい。
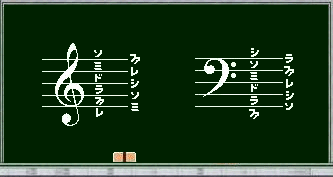
「五線譜カード(共同音楽出版社)」「おんぷカード(くおん出版)」 等のように名刺位の大きさで表に五線が印刷されているカードも市販されています。
裏に指番号なども書き込んで繰り返して読めば短期間に覚えられるでしょう。
また調号
 と臨時記号
と臨時記号 の違いも説明してください。
の違いも説明してください。