 Fホルン
Fホルン  Bbホルン
Bbホルンどの楽器でも共通だと思いますが、楽器にキーや管を増やすと楽器が重くなり同時に鳴りも重く(反応が悪く)なります。キーが何も付いていないナチュラルホルンに比べるとシングルホルンでも鳴りにくくなっています。
音色の好みは別としても、楽器を吹き始める生徒にはシングルホルンの方がいいかもしれません。
一般にF管のホルンは音色が太く、所謂ホルンらしい音と言われています。ただ、高い音域では音のスタートが難しいようです。Bb管はいろんな意味で長所短所が正反対です。
オーケストラではホルンの広い音域をフルに使うことが多いので、この何十年かはダブルホルンを使うのが標準のようになっていて、特に高い音域を多く使うパートではハイF管と呼ばれる普通のF管よりオクターブ高い(管の長さが半分の)楽器も使われます。ダブルホルンにハイF管を組み合わせたトリプルホルンというのもこの頃では珍しくありません。
一方、小学校の吹奏楽で使われるホルンの音域はあまり広くないので、どちらかのシングルホルンでも十分吹くことが出来ます。でも学校にダブルホルンがあるならそのメリットを十分に活かすために両方のホルンの運指を覚えましょう。
下の表がダブルホルン(in F)の基本的な運指です。他の金管楽器と同じように1+2は3でも吹けます(音程が少し低めになります)。
音符の上がBb管、下がF管の指です。最後の低いF( 実音Bb ) はF管では出ません。
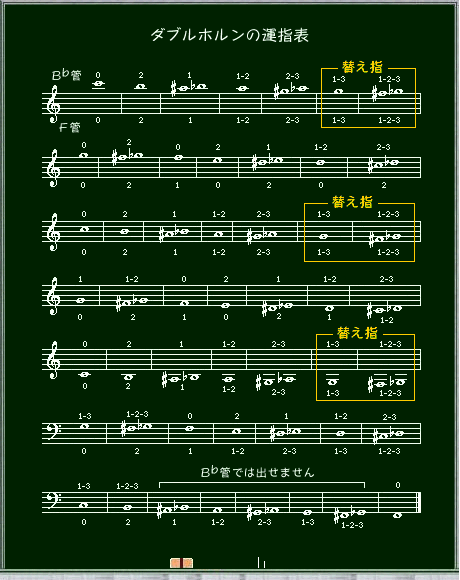
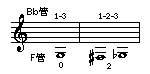 とド
とド やソ
やソ だけF管を使うという人もいて、そのために、親指のレバーを押さえた時にF管になるように楽器をセットしている人もいます(普通は押さえるとBb管、放すとF管になっています)。ヨーロッパのオーケストラではこういう使い方が多いようです。
だけF管を使うという人もいて、そのために、親指のレバーを押さえた時にF管になるように楽器をセットしている人もいます(普通は押さえるとBb管、放すとF管になっています)。ヨーロッパのオーケストラではこういう使い方が多いようです。実際にはF管とBb管の運指の組み合わせは演奏する人の音色の好みや曲の中での前後の音によって様々です。